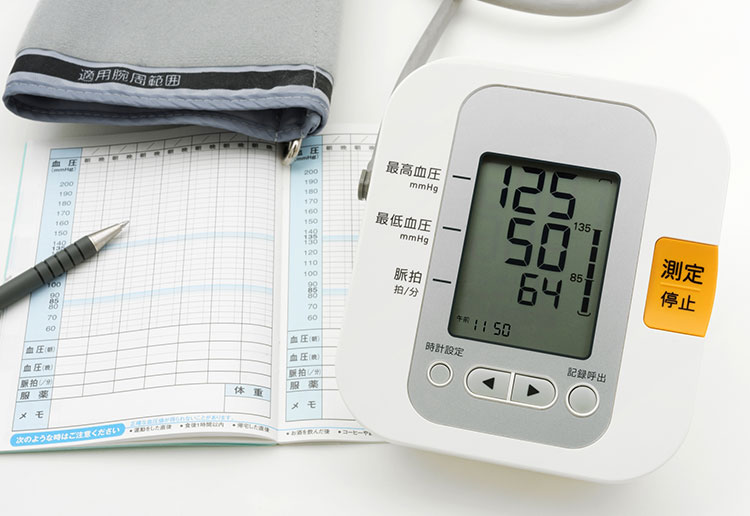くろかわ内科クリニック 施設基準等について
基本診療料
外来感染対策向上加算
当院では下記の院内感染防止対策を取り組んでいます。
- 院内感染管理者(院長)を配置し、職員一同で院内感染対策に取り組んでいます。
- 感染防止対策業務指針及び手順書を作成し、職員全員がそれに従い院内感染対策に取り組んでいます。
- 職員全員に対し年2回院内研修を実施し、感染防止に対する知識向上に取り組んでいます。
- 感染性の高い疾患(インフルエンザや新型コロナウイルス感染症など)が疑われる場合は一般診療の方と導線を分けた診療スペースを確保して対応します。
サーベイランス強化加算
当院では地域や全国のサーベイランス(感染症の監視・調査)に参加し、感染防止対策に資する情報を提供する体制を整えております。
医療DX推進体制整備加算
当院はオンライン資格確認を行う体制を有しており、受診歴・薬剤情報・特定健診情報・その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行っております。マイナ保険証利用を促進するなど医療DXの推進により質の高い医療の提供に努めております。また、電子処方箋の発行や電子カルテ情報共有サービスなど医療DXにかかる取り組みを実施しております。
特掲診療料
- 糖尿病合併症管理料
- 別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所
- 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
- 神経学的検査
- 外来・在宅ベースアップ評価料(1)
- ニコチン依存症管理料
その他
明細書発行体制等加算
当院では医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進するため、使用した薬剤の名称や
行われた検査の名称を記載した明細書を領収書の発行の際に無料で発行しています。
一般名処方管理加算
当院では、令和6年11月25日より後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しております。後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(※一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名処方加算1(10点)後発医薬品が存在する全ての医薬品が一般処方されている場合
一般名処方加算2(8点) 後発医薬品が存在する先発品のうち1品目でも一般処方された場合
長期処方(28日以上)、リフィル処方箋対応
医療情報加算
当院はオンライン資格確認を行う体制を有しています。また、当該保険医療機関を受診した患者様に対し受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行っています。
長期収載品の処方について
後発医薬品(ジェネリック医薬品)について、医師の指示ではなく患者様のご希望により先発医薬品をご希望された場合、薬局でのお支払いで選定療養費が発生致します。
2025年9月現在